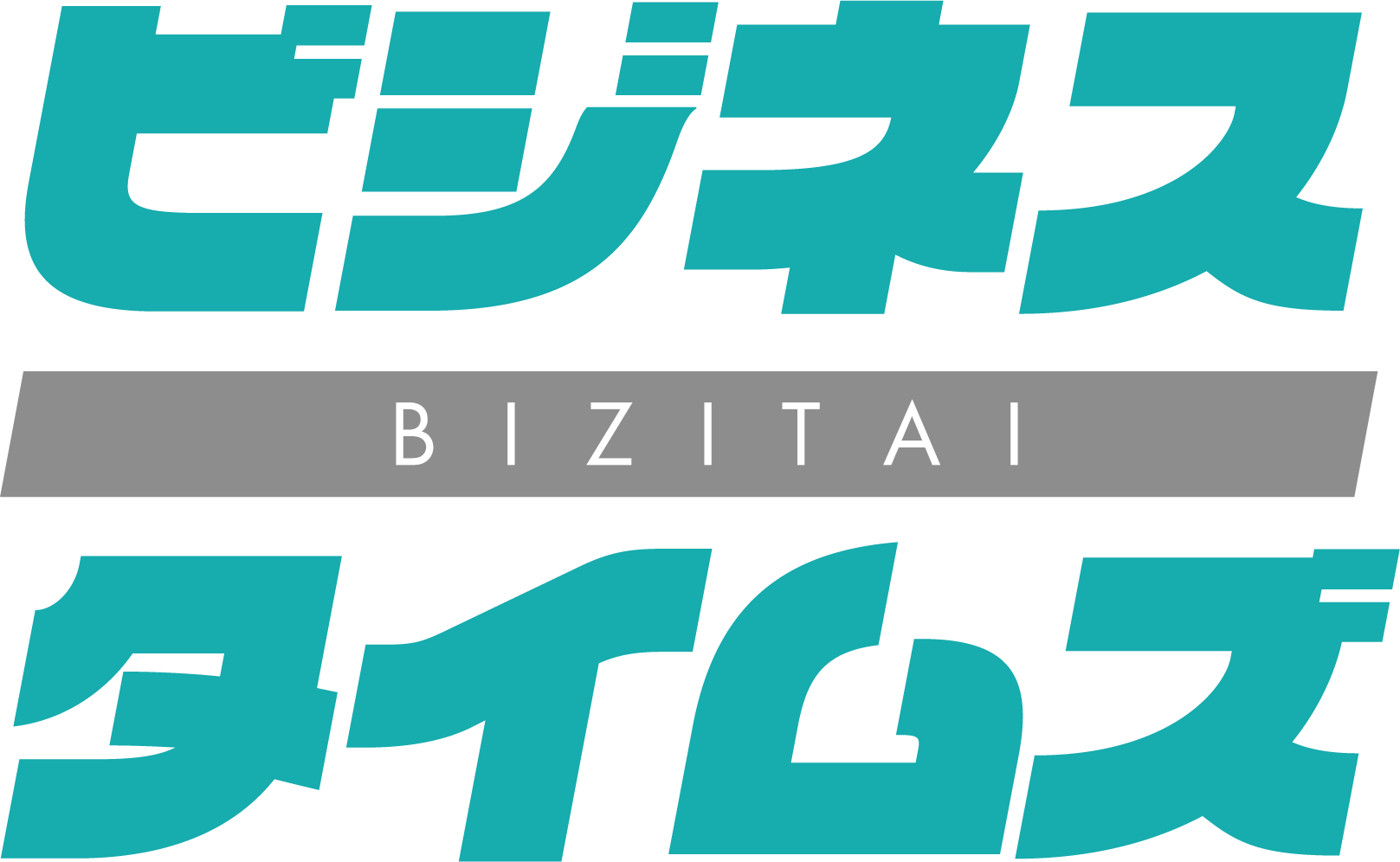医師を志し、経験を積む毎日
サラリーマンの父と専業主婦の母のもとで育った私は、医師の道とは無縁の環境で育ちました。しかし幼い頃、掛かりつけの開業医が嫌な顔一つせず治療をしてくれる姿を見ているうち、医師という職業に憧れを抱くようになったのです。
とはいえ鳥取大学の医学部に進学してからは、人一倍勉強したわけでもなく、部活動やプライベートの時間に重きを割いているような、どこにでもいる平凡な学生生活を送っていました。しかし大学4年生の時にたまたまアメリカ海軍の病院へ見学に行く機会があり、救急医のかっこよさに惹かれるようになっていったのです。卒業してすぐに外科の門を叩き、救急医への道を志すようになりました。
医師になって3年目には自ら志願し、日本の救急医療の中心的な役割を果たしていた千里救命救急センターに移っています。鳥取大学に救急を学ぶ所がなかったためでした。
それから間もなくして大阪・池田小学校の殺傷事件が起こり、2005年にはJR福知山線の電車脱線事故が発生。さまざまな悲惨な現場の医療指揮をとっていく中で、救急医としての礎を築いていったのです。
現場でしか知り得ない救急医療
医師は職人であると私は思っています。だからこそ、いかに現場を経験して自分の技術と知識を増やしていくのかが重要なのではないでしょうか。机上で勉強するだけでは生身の患者を救うことはできないのです。
私が医師になって20年以上が経ちますが、毎日がエキサイティングでした。現場でしか知り得ない新しい挑戦に溢れています。発見や学びの連続の中で、「この人はどうしたら助けられるのか」というゴールを設定し、ただただそこへ突き進むように治療と向き合ってきました。そのためにはクリエイティブな発想も必要ですし、自分の持っている技術と知識をフルに活用しなければいけません。私にとってはそれが原動力であり、医師の醍醐味でもあると感じています。
救急医が命を救うことを諦めてしまえば、人の命もそこで終わってしまう。我々センターのポリシーは「常にフルスイング」であることですが、救急医療はフルスイングをしなければ成果が表れてこない現場であると思うのです。
現在は役職や年齢と共に管理職的な業務も増えてしまいましたが、今後も気力・体力が続く限り、現場に出続けていくことが私の務めだと思っています。そしてあらゆる医療体制や仕組みづくりを進めていくことが、今後の大切な役割でもあるでしょう。実際に2010年に現センターを立ち上げた際には、同年にドクターヘリ事業も設置しました。当時は年間360日ドクターヘリに乗り、救命救急センターに寝泊まりするような生活。それが但馬救急センターの方針や体制づくりの原点となっていったのです。
医療に終わりはありません。これからも現場第一主義を貫き、経験と知識を蓄えながら医療の充実を図っていきたいと思っています。