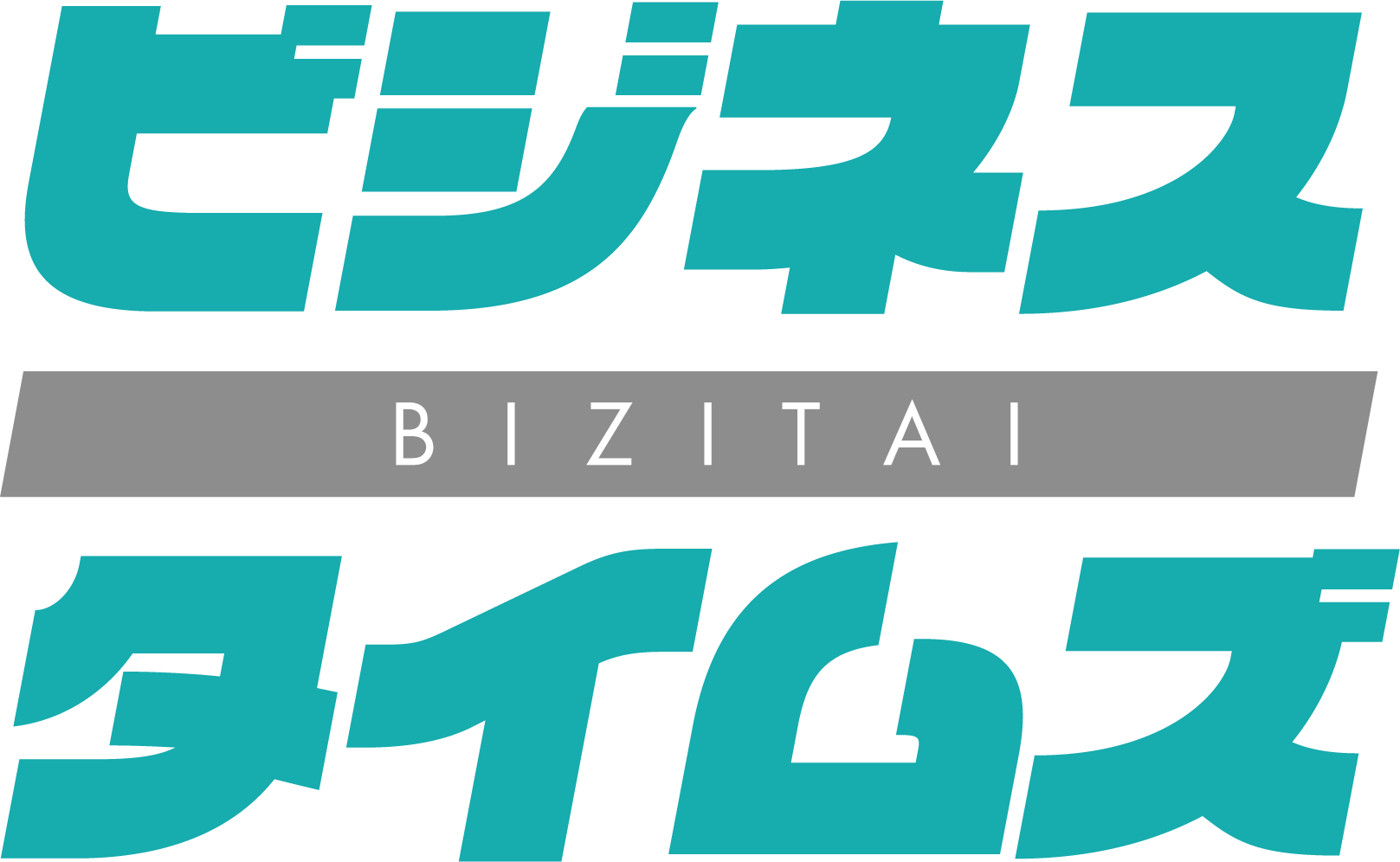現在の仕事についた経緯
AIに興味を持ったのは高校生の頃で、大学では情報理工系の学科に進学し、AIの研究に取り組みたいと考えていました。しかし、大学入学後にインターンや独学を通じて学んでいく中で、「AIの研究開発そのもの」だけでなく、「AIが社会に自然に溶け込んでいる状態を創り出すこと」にも強い関心があることに気づきました。
そのような中で、共同研究プロジェクトのプロジェクトマネージャー(PM)を任せていただく機会に恵まれました。大手企業との大規模なAI開発プロジェクトを通じて、AIの社会実装について一定の経験を積むことができたと感じています。
そして、AIがより迅速に社会に実装される未来を自らの手で実現したいという想いから、Portus AIを創業しました。
仕事へのこだわり
「多数のトレードオフのバランスを考えること」と「抽象と具体を使い分けること」を意識しています。
「多数のトレードオフのバランスを考えること」は、仕事上でのあらゆる判断を行うにあたっての考え方の軸になると思っています。たとえば、「早さと丁寧さ」「独自性と一般性」「コストとクオリティ」など、多数の両立し難い要素が常に存在します。あるプロジェクトで納期を優先すれば品質に妥協が生じるかもしれませんし、逆に高品質を追求するとコストや時間が膨らむことがあります。こうしたトレードオフを無視して一方だけを重視すると、結果的にプロジェクト全体の成功に影響を及ぼすことが多いです。だからこそ、あらゆる判断に関わる正しいトレードオフの関係をリストアップできること、そしてその中で最も適切なバランスポイントを選択できることが重要だと考えています。
また、「抽象と具体を使い分けること」は、複雑な状況を理解し、適切な行動を取るために不可欠だと考えています。たとえば、提案の有効性を考えるとき、まずは抽象的なレベルで市場全体の動向や競合の状況を俯瞰し、提案の骨子を描きます。その上で、具体的な顧客ニーズや現場の課題、技術的な制約など細部に落とし込んでいくことで、実現可能な計画が立てられます。逆に、具体ばかりに捉われると視野が狭くなり本質的な課題を見失う恐れがありますし、抽象的すぎると現実との乖離が生じてしまいます。このため、状況やフェーズに応じて抽象と具体を適切に切り替え、両者の間でバランスをとることが、全体像と現場のギャップを埋めながら効果的な意思決定や問題解決を行う上で非常に重要だと考えています。
若者へのメッセージ
私自身今21歳なので、偉そうに言えることは何もありませんが、巷でよく言われる「若さが武器」という言葉はどういう観点で武器なのかよく考えることがあります。
確かに、若さには体力や好奇心、失敗してもリカバリーが効きやすいなどの要素が含まれていると思います。体力面では長時間の作業や突発的なタスクにも柔軟に対応でき、集中力を維持しやすいです。精神的にも「とにかくやってみよう」というチャレンジ精神が湧きやすく、失敗を学びに変えるリスク許容度の高さは武器かなと思います。さらに、新しい技術や知識を素早く吸収し、自分の成長に結びつける学習スピードも大きなアドバンテージです。経験則に頼ることなく、一歩先を行く発想を生み出せることもあるかと思います。
一方で、判断材料が不足しがちでもあります。経験則に頼ることがないというのはメリットにもなり得ますが、経験的にわかっていることも世の中にはたくさんあります。柔軟な発想を重要視するべきところ、経験則に従うべきところはどこなのか、しっかり考えないと若さも大きな足枷になるなと日々仕事をさせていただく中で思っています。若さが故の柔軟性をクリエイティビティと直結させるだけでなく、謙虚に経験則を受け入れることができて初めて、真に若さが武器になるのかなと考えています。