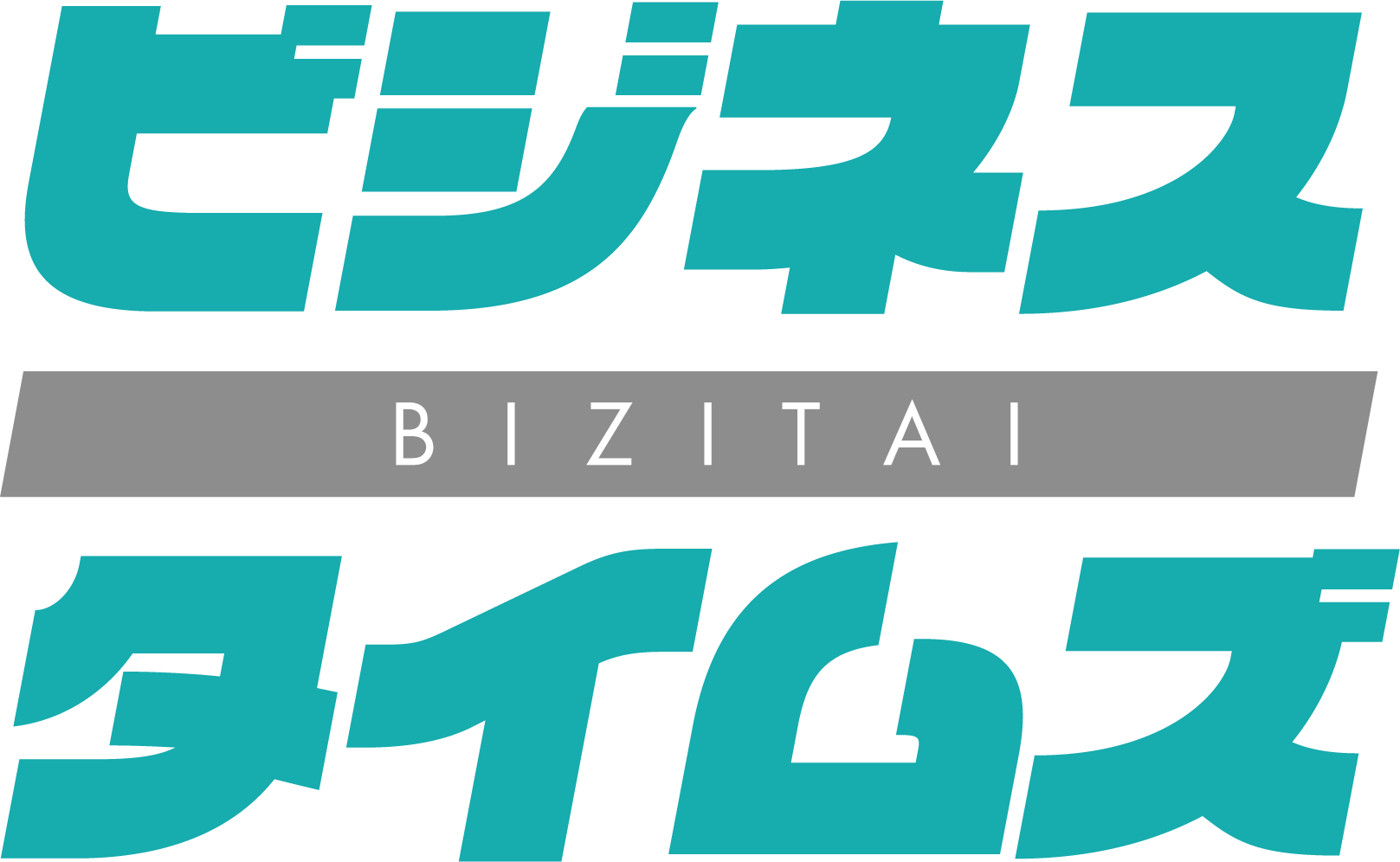現在の仕事についた経緯
都内で月2万円の築60年超の賃貸に住んでいた経験から、貧しく限られた環境でも古き良きものを活かし、工夫しながら自分らしい暮らしを築くことの大切さを実感しました。
その中で自然と中古品の売買に興味を持つようになり、建築・土木領域での勤務経験を活かして、工務店様・職人様の中古電動工具を専門に扱う買取店を立ち上げました。
現在はサイバーエージェント・キャピタル、Dual Bridge Capital、NESなどが運営するファンドから、累計約1億円の資金調達を実施。リユース分野やマーケティング分野に精通するパートナーの支援を受けながら、リユース市場で新たな挑戦を続けています。
仕事へのこだわり
会社員時代から現在に至るまで、私は常に「お客様の課題をどう解決し、疑問を持たずに継続していただくか」を意識して取り組んできました。
特に、「お客様の生の声を聞く(N1インタビュー)こと」と「課題と期待値を正確に把握すること」を大切にしています。
例えば、お客様から課題をヒアリングしたうえで、自社が提供するサービスで解決できると判断した場合は、積極的にご提案します。その結果、お客様に「他のサービスにはないメリットが得られる!ぜひ利用したい。」と感じていただけることもあります。
しかし、時間が経つと、費用面の懸念や、サービス単独ではカバーしきれない部分が見えてくることもあります。そんな時、お客様に「きちんと説明を受けていない」「騙された」と被害者意識を持たれてしまう可能性も否定できません。
せっかく丁寧に提案し、契約まで進めたにもかかわらず、「言った・言わない」のトラブルに発展してしまっては、すべてが台無しです。だからこそ、単に課題をヒアリングするだけでなく、期待値もしっかり把握することを常に心掛けています。
また、起業家となった現在は、「お客様が自らお金を払ってでも解決したい課題」を的確に捉え、たとえお客様自身が気づいていない方法であっても、課題解決の道筋を提示(サービス提供)することに力を入れています。
私にとって、事業創造において最も大切なのは「課題の存在」です。そもそも事業とは、世の中に存在する課題を解決するために行うものだと考えています。
さらに競合との差別化には、「独自性」と「便益(ベネフィット)」が不可欠です。これらを備えたサービスを生み出すためには、「質の高い課題」を発見することが必要です。その第一条件は、課題に対する解像度を高めることです。
例えば「腰が痛い」という漠然とした訴えの中にも、「姿勢が悪い」「可動域が狭くなっている」など、さまざまな具体的課題が隠れています。
このように、本当にお客様が求めているマス層のコアな課題、かつ十分に解決されていない領域を探し続けることが、事業成長の鍵だと私は考えています。
たとえ事業規模が大きくなったとしても、この思考を忘れずに持ち続けたいと思っています。
この記事をご覧いただいた方は、ぜひ私と一緒にディスカッションしましょう!
若者へのメッセージ
私たちは、専門中古品を手間なく簡単に売却できるサービス「ココウル」を運営しています。
「ココウル」は、不要になった中古品に対して、オンラインにて専門家による詳細な査定と買取金額の提示を受けられ、あとは近所のお店に持ち込むだけで売却が完了する、画期的な中古品買取支援サービスです。
独自に開発したオンライン査定ツールを活用することで、ゴルフグッズなど専門用品のスピーディーかつ適切な査定を実現しています。また、ゴルフ練習場など全国の既存店舗と提携することで、「ココウル」の持ち込み窓口を各地に展開しています。
ゴルフクラブの買取といえば、大手中古ゴルフショップへの持ち込みが一般的とされてきました。しかし、私たちは提携するゴルフ練習場に通うお客様一人ひとりに丁寧にヒアリングを重ねる中で、業界の慣習だけでは拾いきれていないマス層のお客様が確実に存在していることに気づきました。
そのようなお客様に対して、どのようなビジネスモデルと料金体系を提示すれば、継続的にご利用いただけるのか。頭から熱が出るほどに徹底的に考え抜き、そして実際にお客様に提案を試してみることが、何よりも重要だと考えています。
皆さんもぜひ、そんなお客様の声に真摯に耳を傾け、ご自身でもビジネスの感性を磨いていってください。