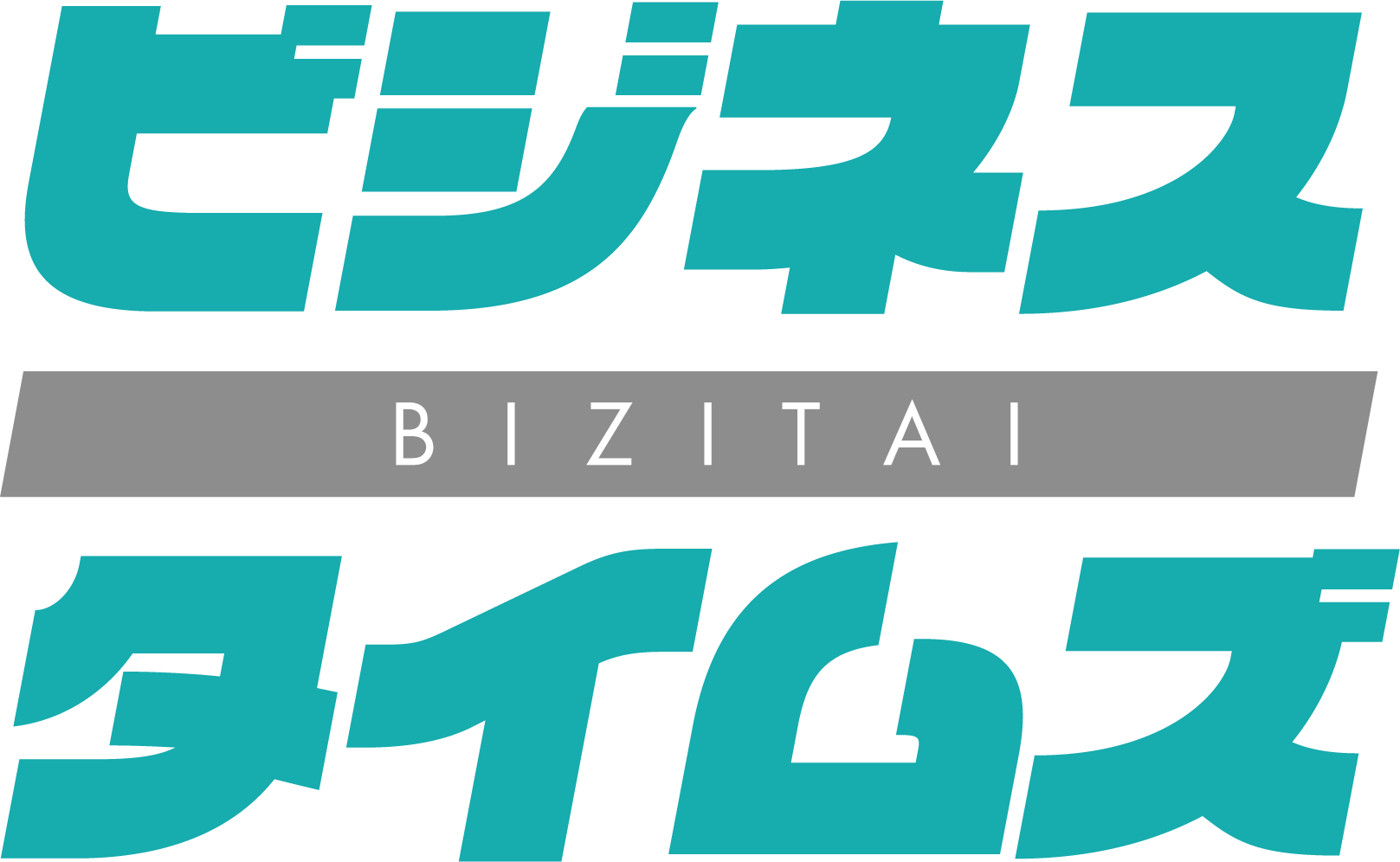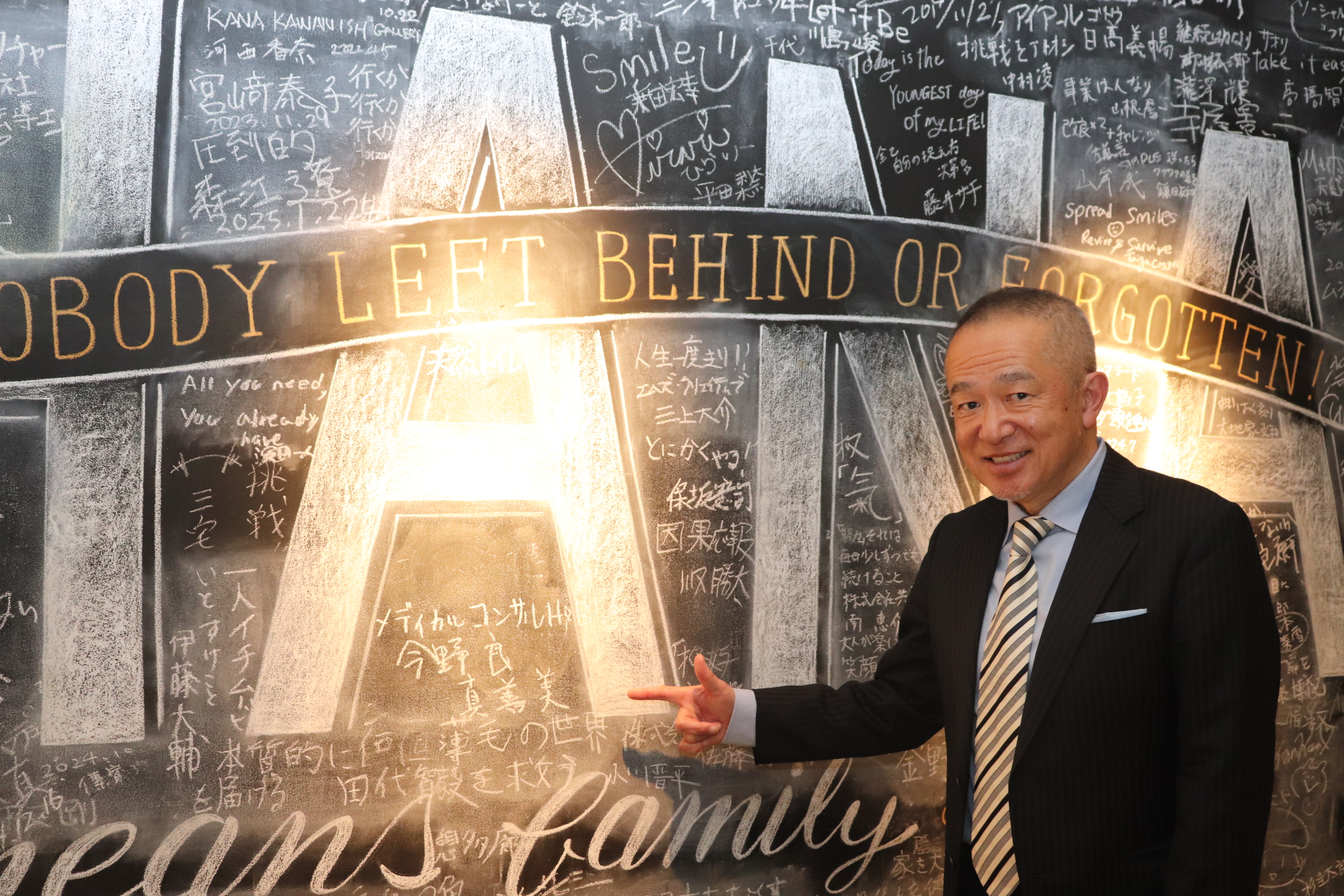現在の仕事についた経緯
「健康と美」は誰しも求めるものですが、年齢にかかわらず大きなテーマです。最近は若い女性も、中高生時から化粧に興味を持ち、エステ、美容外科と「エスカレート」する人もいます。中には、その施術や治療の過程で副作用や予期せぬトラブルに遭遇し、行き場が見当たらず「難民化」、または、その施術にのめり込むといった問題も生じます。
健康と美は中高年女性にも若年層以上の大きなニーズがあります。寿命が延び、若々しく活動する女性達は、年齢を感じさせない美しさを保っています。しかし閉経年齢は以前と変わらず、50~51歳です。見方を変えれば、更年期障害を経て、さまざまな心身の問題を抱えつつも、美しく健康でいようと望み、そのための努力をしている女性が増えているということです。
今回、私はクリニック開業ではなく、個人へのカウンセリングと企業・組織・団体へのコンサルティングを行う事務所を立ち上げました。設立の意図は、若年層には美容という窓口から健康をつくっていくことの重要さを伝えること、中高年女性には正しい情報に基づいて健康で美しいライフスタイルの構築を提案していくことです。そして、研究とその成果の企業や社会に対する発信によって、次世代の「健康と美」の医療・医学に貢献していきたいと考えています。
仕事へのこだわり
ワクチン接種、妊婦健診やがん検診など、common diseasesであるかぜや日ごろの健康問題を扱うのは、先進国に限らず多くの国では「総合医」といわれるかかりつけ医の仕事です。へき地医療に従事した経験からこの「総合医」の重要さは痛感しています。
予防接種は乳児期以降、思春期もその後もかかりつけ医で受けます。子宮筋腫、高血圧、心臓病なども、まずかかりつけ医を受診し、手術や高度医療が必要な場合に専門病院に紹介されます。日本では「頭痛」の際に大学病院でMRIやCTを受けて脳外科医と神経内科医を受診し、最後はマッサージで肩凝りが直ったなど、笑えない非効率的な医療が日常茶飯事です。
これらの背景には、日本の医療を根源から見直し、改善すべき点があります。私が40年間取り組んできた子宮頸がん予防において、今ではヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンも、HPV検診も国の施策・指針になりましたが、依然知らない人の方が圧倒的に多いのが現状です。WHOが進める今世紀中の世界からの子宮頸がん征圧(根絶)は、先進国では数年以内に現実化し、多くの中低所得国でも今世紀中に達成できる見込みです。
しかし日本では数年以内どころか、今世紀中の達成は無理なことが確実視され、他の先進国から100年の遅れが想定されます。その間に、多くの女性が子宮頸がんに罹患し、将来の家族を失い、自分の命を失うのです。しかもこのことを国民の多くは知りません。
HPVは子宮頸がんの原因になるばかりではありません。米国では、子宮頸がん検診の普及によって、HPV関連がんで最も多いがんは中咽頭がん(男女)になっているのです。かつての常識は常識でなくなります。正しい情報を発信し、国民を啓発・教育することが重要です。
この20年間取り組んできた子宮内膜症は、病気は痛みと不妊症が主な症状で、世界中で1億9000万人が苦しんでいます。治療には、ホルモン剤が用いられていますが、ホルモン剤使用中は妊娠ができません。しかも、ホルモン剤は子宮内膜症の原因を治療することはできないのです。
私たちの産官学共同研究によるホルモンに依存しない免疫からのアプローチで新薬開発に取り組んできた成果が、CNNをはじめ世界で50以上のメデイアに取り上げられました。現在、ヒトへの臨床試験が進行中です。
若者へのメッセージ
若い医師時代は決して恵まれた環境にあったわけではありません。むしろ、同期や友人たちが、先進的な教育機関で学び、留学に旅立っていくとき、へき地で数少ない患者さんに接しながら、コツコツと勉強を重ね論文を書いていました。身近に専門医や特殊な技能を持つ指導医がいない環境でも、機会を捉えて学び、専門医資格や医学博士を獲得しました。自分が専門医になればよいのです。
大学病院で勤務するようになってからは、沢山の患者さんの臨床や手術の機会に恵まれて研鑽を積みました。当時は、日本では初めての技術や手術を身に着けられることに感動しつつ、その成果を発信することを覚えました。
医学・医療には、ここがゴールということはありません。学校で教わらなかった、国家試験には出題されない範囲だった、などという言い訳は通用しないのです。患者さんには、個人ごとに最高の医療と配慮を提供すべきです。
現在、利用できない医療は、臨床試験や研究開発で作っていくしかありません。グローバルにあって、日本にないものがどんどん増えてきています。日本はもはや先進国ではありません。この状況にあって、井の中の蛙でぬくぬくと生きていくことが望ましいことではないのです。
個人に対する医療の個別化も重要ですが、一方で、公衆衛生の価値を重要視してほしいと思います。小医は病を医す、中医は人を医す、大医は国を医す。自分の制限(limitation)を自分で作ってしまうことは避けよう。どんな可能性もあるのだから。